尻に火がついた永守日本電産
M&Aの旗手、永守社長に相次ぐ「黒星」。世界同時不況の直撃を受けた本業が危ない。
2009年2月号 BUSINESS
初めての買収失敗は拡大路線の屈折点か――。積極果敢なM&A戦略で急成長を遂げた中小型モーターの世界的企業、日本電産の前途を危ぶむ声が上がっている。ここ数年、永守重信社長のカリスマ性も手伝って快進撃を続け注目企業になっていた。ノートパソコンに搭載する精密小型モーターで圧倒的な世界シェアを築くなか、コパル電子、三協精機製作所、日本サーボなどをM&Aによって次々に子会社化。連結売上高「1兆円企業」の仲間入りを視野に入れていた。
永守社長が「進軍ラッパ」を吹いたのは昨年9月16日夜。今度は鉄道用機器メーカーの東洋電機製造(東証1部上場)にTOB(株式公開買い付け)による子会社化を提案し、その事実を公表するという攻勢に出た。これまで日本電産は被買収企業と合意の上でM&Aの経緯を発表する友好的な買収路線を貫いてきた。ところが、今回は東洋電機製造の意向は一顧だにせず、買収提案と条件を一方的に世間に知らせるという強硬なやり方だった。
「東洋電機」買収断念の舞台裏
「買収案はベストな提案。(東洋電機製造に)受け入れてもらえる」という、永守氏の自信満々の記者会見もさることながら、TOB価格が一株635円という高値だったため東洋電機製造に「提灯買い」が殺到。買収提案発表直前に285円で引けていた株価は翌17日、18日は売買不成立。19日には一挙に525円まで噴き上がった。
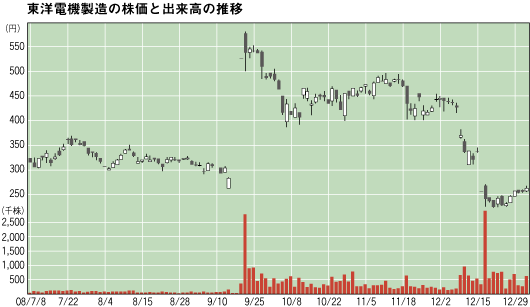
日本電産の買収提案に東洋電機製造が度肝を抜かれたのも無理はない。両社のメーンバンクである三菱東京UFJ銀行の副頭取からの連絡も唐突だったうえ、16日当日に社長同士の面会を申し込み、同日夜の記者会見で買収提案を発表するやり方は、まさに「青天の霹靂」だった。
しかし、仰天したのは東洋電機製造だけではなかった。車両モーター、運転制御装置、パンタグラフなどの製品供給を受けている鉄道業界にも衝撃が走った。大手電鉄会社の技術部門役員は、こう憤慨する。
「鉄道車両モーターは電鉄会社と製造会社による共同開発のようなもの。製品を納入した後も延々とメンテナンスが続く。効率性の追求で業績を伸ばしてきた日本電産の小型モーターと、安全第一の鉄道車両モーターとではビジネスモデルがまるで異なる。もし、東洋電機製造が買収されたら、電鉄会社側に取引を見直す動きが出るのは間違いない」
電鉄業界には、効率第一の外資系電機メーカーから試験的に製品を購入した関東の私鉄が、継続的なメンテナンスを受けられずに苦労したエピソードが残っているだけに懸念を募らせたわけだ。
一方、日本電産から買収提案を突きつけられた東洋電機製造は、幾度も買収提案に関する必要情報の提供を求め続けた。12月5日には日本電産の永守社長と東洋電機製造の大澤輝之社長によるトップ会談。さらに12月11日には、両社の技術部門、労務・財務部門の役員が面談。日本電産は買収提案の妥当性をアピールする目論見だったが、肝心の買収のシナジー効果について、東洋電機製造側に満足な回答を示せずじまいだった。かくして買収提案の有効期限である12月15日が迫ってきたが、両社の溝は深まるばかり。「業を煮やした永守社長は敵対的買収に打って出るのではないか」との観測が立ち始めた。
ところが、電鉄業界をも不安の渦に巻き込んだ買収攻勢は、実にあっけない幕切れを迎えた。12月15日、日本電産が突如、買収を断念すると発表したからだ。もともと一方的な買収提案であり、敵対的買収への警戒を強めていた東洋電機製造にとっては予想もしない展開だった。それどころか、日本電産からは交渉を続けてきた東洋電機製造に一言の連絡もなかった。他人の家に土足で上がり込んだうえに、何の挨拶もなく去っていったのだ。ハゲタカファンドならいざ知らず、モーター業界最大手の上場企業が取るべき行動か。この一件はM&A常勝軍団・日本電産にとって初めての黒星となった。同日の東洋電機製造株はストップ安となり、東証1部銘柄で最大の値下がり率を記録した。
進軍ラッパに踊らされた株主
実は昨年末の日本電産の「退却」は、東洋電機製造への買収提案だけではなかった。同時に進められてきた富士電機ホールディングスとの資本提携交渉も、12月19日に打ち切られたのだ。富士電機グループの富士電機モータに日本電産が出資し、今年1月1日付で子会社化する計画で、9月30日には富士電機ホールディングスと基本合意に達していたのだが、あえなく白紙に戻った。
富士電機モータの企業価値をめぐって、日本電産と富士電機ホールディングスとの間で折り合いがつかなくなったというのが理由だが「富士電機モータの不良債権問題などを急に持ち出して破談に持っていったようなもの」と業界関係者は指摘する。百発百中の成功率によってM&Aの旗手と持て囃された永守社長に手痛い黒星が続いたことになる。
同日、日本電産は2009年3月期連結決算の業績予想を大幅に下方修正した。売上高は期初予想の8千億円から6300億円に下がり、最終利益は580億円から280億円に半減するという厳しい内容である。販売減は車載、HDD、産業機械、デジタル家電などすべての分野に広がった。昨年10月以降、製品輸出比率の高い同社は世界同時不況の直撃を受け、そもそも買収攻勢に出る経営環境にはなかったのだ。
実際、大晦日の日経新聞朝刊のインタビュー記事に登場した永守氏の発言は驚くほど赤裸々だった。「11月中旬に入り8800社の納入先すべてで受注が落ち込んだ。特に海外の顧客は『キャッシュ・イズ・キング』と言って年末の決算に向けて在庫圧縮に走り、次々と発注先送りやキャンセルをしてきた。12月中旬にさらに落ち込み、(略)12月の全製品の売上高はピークだった9月、10月の5割強の水準となった」。さらに、「黒字を維持できるか、赤字に陥るかが企業存亡の分かれ目だ。1930年頃の世界恐慌に関する書物をむさぼり読んで考えて12項目の不況対策指針を12月1日に社内に出した」とも語っている。
9月の買収提案から年末の断念に至る交渉は、何だったのか。永守社長は「(東洋電機製造は)初めから拒否ありきで買収しても相乗効果が見込めない」などと記者会見で強弁したが、負け犬の遠吠えでしかない。業績が急降下する中では東洋製造電機とのシナジー効果を検討する余裕などなかったはずだ。カリスマ永守が鳴らす進軍ラッパに踊らされた株主が、東洋電機製造の株価に一喜一憂しただけである。
「経済環境の激変が目に入らないワンマン永守の独り相撲」(証券アナリスト)との酷評もある。先の日経インタビューで永守社長は「不況で不振企業が増え、買収額も下がっているため、09年は再び救済型のM&Aに取り組んで行く」と攻めの姿勢を強調するが、買収提案をする前に己の尻に火がついていることに気づくべきだろう。



