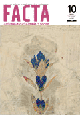美の来歴⑬ この憂鬱(メランコリー)は何処から
〈亡命者〉フジタを拒んだ米国人画家、国吉康雄の戦後
2019年10月号
LIFE
[美の来歴]
by
柴崎信三
(ジャーナリスト)

「バンダナをつけた女」(1936年、カンバス、油彩、福武コレクション、岡山県立美術館蔵)
国吉康雄の女性像、とりわけ1930年代から太平洋戦争期の作品のモデルは、眼差しに深い憂いをたたえている。くすんだ褐色の背景に、翳りを帯びた肌がたおやかな線に包まれて浮かび上がる。代表作の「バンダナをつけた女」の背後から聞こえるのは、戦時体制に向かうマンハッタンの街角を、不安に行き交う異邦人の溜息だろう。
16歳で故郷岡山をほとんど迷うことなく捨て去り、単身で太平洋を渡った。サンフランシスコやロサンゼルスで鉄道の洗車作業員や農家の果物摘みなど、肉体労働のかたわら地元の美術学校に通って絵を描いた。
以降、太平洋戦争を挟んで戦後の1953年にニューヨークで63歳で病死するまで、父親の病気見舞いで故郷に帰国した数カ月を除いて、ついに祖国へ戻ることはなかった。
1906年に国吉が渡った米国は当時、西海岸を中心に日本からの移民がピークをなし、いわゆる黄禍論が高まった時代である。移民の米国籍取得を不可能とする新帰化法が制定されて、日系移民たちを取り巻く環境は厳しさを増していた。
それでもこの若者は米国の自由と豊かさを信じて、働きながら絵を学び、ニューヨークで知り合ったユダヤ系米国人画家、キャサリン・シュミットと結婚して「米国人画家」として生きることを選んだ。
*
国吉の画家としての成功のきっかけは、1922年にニューヨークのダニエル画廊で開いた個展である。「野性の馬」のオリエンタルな筆触と繊細なモダニズムが「ニューヨーク・タイムズ」など多くのメディアで高く評価されて、以降この画廊は毎年国吉の個展を開いた。
米国のモダニズム画家によるサロンズ・オブ・アメリカの会長に選ばれた国吉は1925年、親友のユダヤ系画家、ジュール・パスキンを訪ねてキャサリンとともに初めてパリを訪れた。
その当時を美術評論家の柳亮が雑誌「アトリエ」(1933年12月号)に記している。
〈アメリカの美術史が、その現代編の巻頭に、この国で育った最大の画家に就いて、二つの名を挙げる用意をしているとすれば、それはパスキンとクニヨシの二人だ―と、巴里へ来る紐育の青年達は一斉に答える〉(「ブラボー・クニヨシ」)
国吉がブルガリア出身のパスキンと結んだ格別の友情には、大戦の谷間のニューヨークで同じ移民画家として託(かこ)った「異邦人」の孤独があった。パリに渡ったパスキンはクリシーのアトリエで連日のように饗宴を重ねて、ある日突然自殺する。
「バンダナをつけた女」や「デイリー・ニュース」「休んでいるサーカスの女」など、国吉がこのころ描いた女性像はパスキンの手法が色濃く影を落としている。ダンスホールや酒場やサーカスで働く女性たちの多くは、大都会の片隅に生きる寄る辺ない異邦人であり、その憂いと倦怠は国吉自身に重なる。
世界恐慌が起きて世相が暗転した1929年、国吉はニューヨーク近代美術館(MoMA)の「19人の現代アメリカ画家展」に選ばれた。国籍は得られないものの、「米国人画家」としての「クニヨシ」の名前は国際的にも知られるようになった。
米国内では排日の機運が高まり、西海岸を中心に移民した多くの日系人たちが日米開戦とともに強制収容所に収容されるなかで、国吉は「敵性外国人」の疑惑を免れて戦時下を「米国人画家」として生きのびた。それは単にこの画家が米国を代表する画家のひとりとして、米国社会の高い評価を受けていたことだけが理由ではない。
祖国日本に対するこの画家の眼差しは醒めている。
〈1931年に死にそうな父に会うため日本に帰ったときは、妙に不自然な感じを抱いたのでした。彼らの生き方に合わせるのは、私には難しいことでした。最早、私はここに属していないのだと感じました〉(小澤善雄「太平洋戦争と東部日本人」)
国吉は積極的に米国を支持して日本の侵略戦争を批判した。米国戦時情報局(OWI)の対日宣伝放送にもかかわり、「アメリカは民主的な理念への確信を分かち持つがゆえにここに集まった、あらゆる人種集団の国です。それは人民の大地です」と祖国に向かって呼びかけた。
OWIは国吉に日本軍の残虐な虐待や拷問を描くポスターの制作も求めた。1942年に中国を救済するためにニューヨークで開いた「国吉康雄回顧展」では、首都東京への空爆を容認する発言が報道されたこともある。
開戦下とはいえ、過剰とも見える米国への同調と祖国への敵対は、すでに「米国人画家」として枢要な地位を占めつつあった国吉の、一種の自己防衛がもたらしたのであろうか。
*
戦後も国吉は「米国人画家」として生きた。冷戦体制下の米国内で広がる反共主義の波に揺さぶられながら、1948年にホイットニー美術館で大規模な回顧展が開かれ、52年にはヴェネチア・ビエンナーレに米国代表として出品している。
日本で戦争画の指導的立場に立って責任を問われた藤田嗣治は戦後、祖国を追われて49年に米国へ渡り、ニューヨークに新天地を求めた。その時、接点となったのが国吉である。
藤田にはブルックリン美術学校の教授などのポストが用意されていたが、到着すると帳消しになっている。全米美術家連盟会長の国吉がそこに介在していたと、藤田が記している。
〈迎えに出た二人の友人が、私に気の毒そうな顔をしてこう語った。この話が抑々(そもそも)出た處、国吉氏が大いに邪魔を入れて、私が戦争中軍部に協力した、軍国主義だ等とて、美術学校も恐れを抱いて私を招聘してくれないことになったと言った〉
米国における国吉の立場からすれば、「十二月八日の真珠湾」を描いた藤田の受け入れは到底認められなかったのである。
それにしても、この二人の画家の運命は戦争を挟んで相似形を描いているようである。
藤田が代表作「カフェ」で憂いをたたえた美しい女性像を手掛けたのはこのニューヨークの滞在の時であった。頬杖をついて屈託する若い女性は、国吉の「バンダナをつけた女」のモデルの哀しみにどこかで交差する。
〈戦争〉を挟んだ重苦しい時代への溜息が、そこに通いあっているようである。