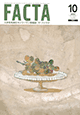さまよえる天才の晩景
レオナルド・ダ・ヴィンチとルネサンスの黄昏
2020年10月号
LIFE
[美の来歴]
by
柴崎信三
(ジャーナリスト)

レオナルド・ダ・ヴィンチ「白貂を抱く貴婦人」(1485-90、板・油彩、ポーランド・クラクフ、チャルトリスキ美術館)
1515年の12月、フランス王フランソワ1世がミラノ公国を占領したとき、レオナルド・ダ・ヴィンチは王を遇するためにローマ教皇レオ10世がボローニャで催した和平の会見に余興を求められて、一興を案じた。
市庁舎3階のフェルネーゼの間でフランソワを出迎えたのは、なんとレオナルドが作った精巧な自動人形の獅子であった。
ばね仕掛けの鋼鉄製の獅子は大広間の貴顕の間を走り抜けると、王の前で立ち止まり、後ろ足で立ち上がって表敬した。やがて獅子の胸が開いて、そこからたくさんの白百合の花が振りまかれた。一同は喝采した。
獅子はレオナルドの故郷、フィレンツェの紋章であり、白百合は占領国フランスの国花である。美術から建築、数学、天文学にいたるまで、あらゆる分野に迸るような叡知を開花させた天才児は、この時63歳。玩具の獅子に何を託したのだろう。
フィレンツェが生んだ万能の鬼才は、若い日からメディチ家の寵愛を受けたが、やがて復興期のイタリアの都市国家の興亡に翻弄されるように、ミラノからローマ、ナポリと各地を渡り歩く歳月を送る。「メディチ家が私を創り、そしてメディチ家が私を台無しにした」という、彼の残した言葉は痛切である。
才能が時の権力に差配される芸術家の運命は、まことに数奇である。レオナルドは獅子の自動人形とともに出迎えたフランソワ1世の絆を頼ってその後、フランス中部のロワール河に沿った古都、アンボワーズという異郷で4年の余生を送り、67歳で生涯を閉じた。それはルネサンスの大才が時代と行き違った不運と呼ぶべきだろうか。
〈彼の仕事のなかに思考や頭脳、精神の大いなる神性が示され、その敏速さ、生気、寛大さ、美しさ、優雅さなど、誰も匹敵するものがいないほど恵まれたものであった。よく知られていることだが、レオナルドはその知性的な技倆により多くのことをはじめたが、何も完成しなかった〉(田中英道訳)
少し下った時代の伝記作家、ジョルジョ・ヴァザーリは『芸術家列伝』に明るく優美な天才の不思議な器量を描いている。
*
フィレンツェでは学芸の保護者で「偉大なロレンツォ」と呼ばれたメディチ家の当主、ロレンツォの庇護を受けた。しかし彼の眼差しはいつも自然と人間を巡る森羅万象の深淵に向かって移ろい続け、約束した教会の絵画や壁画などは未完のままに放棄されることになった。
1481年にローマ教皇庁のシスティーナ礼拝堂を飾る壁画の制作の晴れ舞台に、フィレンツェの政庁が推薦したのはボッティチェッリをはじめとする同世代の4人で、レオナルドの名前はそこになかった。移り気と完全主義が、画家としての信頼を損なったのである。この気まぐれな異才を持て余したロレンツォは彼をミラノへ送った。
1483年、レオナルドが新天地のミラノで当主の公爵、ルドヴィーコ・スフォルツァにあてた自薦状が残されている。
〈名声赫々たる殿下。小生、きわめて軽く、頑丈で、携帯容易な橋梁の計画をもっています。それによって敵を追撃することもできれば、時には退却することも出来ます。ある町の攻囲にあたって、濠の水を浚え、無数の橋梁や上陸用舟艇や雲梯その他かかる攻撃に付属する諸道具を制作することができます〉
10項目の自薦状の最後で、画家はようやく彫刻や絵画などの「本業」の売り込みも忘れていない(『手記』杉浦明平訳)。
レオナルドは軍事技術者として、あるいは土木技師として、時には解剖医として、科学的な研究とその応用に熱中して成果を政庁に次々と売り込んだ。
アルノ川を改修してピサとフィレンツェを結ぶ河川工事に、並外れた構想力を発揮する。あるいは都市防衛のための移動要塞や石礫を使った投擲機などの新たな軍事技術、ヘリコプターの原型の空中移動技術からプレートテクトニクス理論の初歩に至るまで、その知見の広がりは、超人的と呼ぶにふさわしい。
ここでも構想が実際に軍事技術や都市基盤として実現されたものは稀だったが、16年のミラノの歳月は鷹揚なパトロンの下で宮廷行事の演出や音楽家などの多彩な活躍の場を得て、レオナルドの人生に充足をもたらした。森羅万象に向かう「万能人」にとって、絵画はそのための基礎的な作法(メチエ)の一部だったのか。
ミラノ公爵スフォルッツァの下で、レオナルドは生涯を代表する2点の絵画を描いている。1点は修道院の壁画として依頼された「最後の晩餐」である。
キリストが処刑される直前の12人の使徒たちとの会食の場面で、ひとりの裏切者を浮かび上がらせる劇的な構成は圧倒的な画家の力量を見せつけた。
*
もう1つはスフォルッツァの愛妾、チェチリア・ガレラーニを描いた「白貂を抱く貴婦人」である。妻のベアトリーチェと暮らす城内に、公爵が一緒に住まわせたという愛人の、澄んだ美しさを湛えた肖像である。
女性が胸に抱く白貂はスフォルツァ家の紋章であり、1488年にはナポリ王から「白貂の勲位」を受けていることから、この絵は画家の主君に対するひそかな賛辞(トリビュート)であったのだろう。
しかし、ルネサンスの黄昏が近づいていた。「偉大なロレンツォ」の死とメディチ銀行の倒産、過激な教会原理主義者サヴォナローラの台頭とその処刑など、祖国フィレンツェの衰退を、彼はミラノの地で知った。
1516年末、フランス王フランソワ1世の招きで、64歳のレオナルドは真冬のアルプスを越えてフランスへ向かった。
画家はアンボアーズ郊外のクルー城で余生の日々を送った。弟子のサライとメルツィ、それにフィレンツェの裕福な絹商人の妻、ジョコンダを描いた作品「モナ・リザ」を伴った。
現在、1点だけ残るレオナルドの自画像はこの前後に描かれたとみられる。伸びるに任せた髭と皴に緩んだ眼元には、若い日の万能の俊才の面影はない。浮かび上がるのは、夢を追い続けた老年の悔恨だろうか。
「人の世の美しきもの、すぎてとどまらず。労苦は去る。ほとんど目に見えない名声を抱えて」と、レオナルドは記した。
故郷フィレンツェは輝きを失い、見知らぬロワール河の畔に寄る辺ない晩景が広がっている。