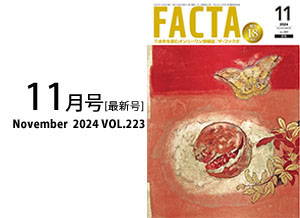コメ流通業者に責任転嫁!/農協と族議員の「しもべ」農水省の大罪
「公僕」としての主体性を失い、消費者を無視する農協と族議員の下請組織に堕落した!
2025年4月号 BUSINESS
霞が関の劣化が言われて久しいが、最近の農水省の惨状は目を覆いたくなるほどである。安倍内閣の時代に農政改革を強力に進めていた農水省とは、まるで別の官庁だ。米は日本人の主食である。その米が、昨年夏にスーパーの店頭から1~2か月も消えたにもかかわらず、100万トンもある備蓄米を放出せず、それによって適正な価格転嫁を超えた異常な価格高騰を作り上げた。半年もたってから、米が流通段階に滞留しているとして、備蓄米の放出を決定するというバカさ加減だ。放出しないよりはした方がよいが、今さら焼け石に水だし、放出の仕方も問題だ。これに関する農水省の説明もひどい。昨年夏は「2023年産は不作ではないのだから備蓄米の放出はできない」「2024年産米が出回れば価格は落ち着く」という説明だったが、嘘八百だったことは明らかだ。
流通業者に責任転嫁
2月に備蓄米放出を決定したときは、「農協系の集荷数量 ………
ログイン
オンラインサービスをご利用いただくには会員認証が必要です。
IDとパスワードをご入力のうえ、ログインしてください。
FACTA onlineは購読者限定のオンライン会員サービス(無料)です。年間定期購読をご契約の方は「最新号含む過去12号分の記事全文」を閲覧いただけます。オンライン会員登録がお済みでない方はこちらからお手続きください(※オンライン会員サービスの詳細はこちらをご覧ください)。