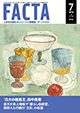新ビジネス誕生の壁「著作権法」
米国はフェアユースの概念で権利を制限し価値の創造を後押し。日本は既得権者第一。
2018年7月号 BUSINESS

「青空文庫」のトップページには、70年への保護期間延長反対のロゴが掲げられている
5月18日、改正著作権法が成立した。文科省の資料によると、最大の目玉は「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」とある。つまり、「ネット時代に対応した著作権法」というのが最大の売りだという。
だが、日米の著作権事情に詳しいある弁護士は落胆の色をにじませながら「対症療法的な立法がイノベーション(価値の創造)を阻害していることにいつになったら気付くのか」と話す。
日本の著作権法は、海外から黒船の如く押し寄せる、ネット時代の新しいビジネススキームにお尻を叩かれるように、常に後追いで改正対応してきた。今回もまったく同じ轍を踏んでおり、「柔軟な権利制限規定」と謳いつつ、既得権者におもねる内容に終始しているというのだ。
ネット時代を迎え、米国で新しいサービスが次々と登場するのは、米著作権法の「フェアユース」という考え方の存在が大きい。フェアユースは、公正(フェア)な利用(ユース)であれば、著作権者の許諾なく、著作物の利用を認める規定だ。これがあるから、米国のスタートアップ企業は、新しいビジネスに挑戦し、イノベーションを作り出すことができる。
グーグルの検索に連動した広告ビジネスがまさにこれだった。1990年代後半、世界中のウェブサイトの情報を権利者の許諾を得ることなく自社サーバーに保存(キャッシュ)し、包括的かつ網羅的な検索ニーズに対応することで、検索キーワードそのものに広告価値を付加するという、ネット時代ならではのビジネスとして成功した。
グーグルから「14年遅れ」
発足当時、グレーだったこの手法に米国の司法当局は、フェアユースを認めた。振り返って考えるとその頃は、検索エンジンの技術は日本も決して劣っていなかった。しかし、日本の著作権法は、情報をキャッシュする際、すべての権利者の許諾を得なければならないとしていた。その結果、日本のポータルサイトは米国の検索エンジンを利用せざるを得ず、この分野は米国勢に席巻された。
日本政府もさすがにまずいと思ったか、2009年の著作権法改正で「検索キャッシュ」を合法化した。だが、時すでに遅しだった。ある日本人ベンチャーキャピタリストは「魅力的なネットサービスのプランに出会っても著作権の扱いがグレーだと投資に尻込みする」と打ち明ける。米国型のフェアユース規定がない日本では、著作権リスクが完全にシロか、膨大なコストと時間をかけて許諾を得ないと何も始められないのだ。
今回の改正で、文科省が「柔軟」の例にあげているのが、書籍や論文の内容を権利者の許諾なしに電子化しサーバーに保存することを許す「所在検索サービス」への対応だ。
ユーザーが特定のキーワードで検索した際、そのキーワードに関係する内容が、どの書籍の何ページに記載されているのかがわかるサービスが、権利者の許諾なしに可能になる。
だが、これとてグーグルは04年にもう「Google Books」と称する同様の取り組みを始め、すでに軌道に乗せている。日本の所在検索サービスは検索キャッシュ同様、周回遅れなのだ。
米国版フェアユースは、日本のような個別の目的限定ではなく、そのシンプルさと懐の深さから、真の意味での柔軟な対応を可能にしている。実際、米司法当局は、技術進化を横目でにらみながら、イノベーションを阻害しないよう、その時代に寄り添った判断をフェアユース規定のもとで下してきた。グーグルが図書館書籍の全文を電子化する事業が裁判になった際も、裁判官は「著作権法の受益者は利用者でなければならない。古いビジネスモデルを守るためにあるのではない」と明言した。
一方、日本では著作権法の「権利制限規定」の改正のたびに「日本版フェアユース」と銘打たれるのだが、改正の中身はそのたびに権利者や権利団体の抵抗の前に骨抜きにされてきた。
文化庁の著作権関連審議会メンバーの顔ぶれを見ると、権利団体代表、御用学者、御用弁護士の名前で埋め尽くされているから、無理からぬ話なのだが、日本の著作権法は、旧態依然としたビジネスモデルと既得権を死守するためにあるのだ。
「三島由紀夫」無料化お預け
著作権法関連では、近いうちにもう一件大きな動きがある。著作権の保護期間の50年から70年への延長だ。3月に日本を含む11カ国の閣僚が署名したTPP11(環太平洋連携協定)が、正式に発効すると、保護期間延長が自動的に施行される。
そうなると、まもなく死後50年を迎え、無料で楽しめるはずの、三島由紀夫(1970年没)、志賀直哉(71年没)、川端康成(72年没)といった近代の大文豪たちの作品のパブリックドメイン(PD=公有物)化が一気に遠のいてしまう。
16年にPDとなった谷崎潤一郎や江戸川乱歩の作品は、有志の手でデータ化が進められネット上の電子図書館「青空文庫」で自由に楽しむことができる。志賀直哉や川端康成の一部作品は、出版社が有料の電子書籍を販売しているが、三島由紀夫の作品は電子化がほとんど進んでいない状態だけに21年の「喪明け」への期待が大きかった。
なぜ、TPP11と著作権の保護期間延長が関係するのか。米国を含む12カ国が参加した前回のTPPでは、米国が保護期間延長をねじ込んできた。ハリウッド映画などの輸出で著作権貿易収支が黒字の米国としては、延長することで優位性がさらに増す。トランプ政権がTPPを離脱したことで保護期間延長は「凍結」扱いになったはずだったが、交渉のカードに利用されたり、延長を推進する権利者サイドのロビー活動が行われたりする中で、延長案件は有効なままだった。
日本の一部作家や権利団体にとって保護期間延長は、20年越しの悲願だが、米国における保護期間の50年から70年への延長は、ミッキーマウスのPD化が迫っていたウォルト・ディズニー・カンパニーのロビー活動が背景にあったとされる。
保護期間の延長で利益を得られるのは一部の出版社とごく一部の作家遺族だけ。年々拡大している日本の著作権貿易収支の赤字が、保護期間延長によりさらに増えるのは確実だ。
PD化が遠のくことの社会的損失はさらに大きい。加盟11カ国の国内手続きが完了した時点で70年延長が確定する。米の裁判官の言葉を再度引用しよう。「著作権法の受益者は、利用者でなければならい」