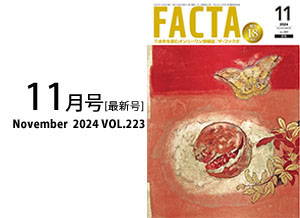万博開幕/初の水素旅客船「まほろば」に「リアル沈黙の艦隊」の夢!
海上自衛隊が水素燃料電池技術と「ヤマト1」の超伝導電磁推進技術を組み合わせた潜水艦を建造すれば……。
2025年5月号 BUSINESS

水素燃料電池船「まほろば」(岩谷産業HPより)
岩谷産業は3月21日、水素燃料電池船「まほろば」の完成披露式典を開いた。2025年国際博覧会(大阪・関西万博)では大阪都心部の中之島からユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)に近接するユニバーサルシティポートを経由して会場の夢洲(ゆめしま)に至る海上アクセスを担う。
船体はアルミ合金製の双胴船。デザインを担当したカーデザイナーの山本卓身氏は「最初から双胴船と決めていた」という。少ない排水量でも広い甲板が取れ、風に流されにくく高速航行中の安定性が高いからだ。
全長33m、幅8m、2階建てで定員は150人。航続距離は約130㎞で時速約20㎞を出せる。最大の特徴は容量230ℓの圧縮水素ボンベ16本、出力60kWの燃料電池4基、容量1000kW時のリチウムイオン電池を積み、その電気でモーターを駆動してスクリューを回す。船につきもののディーゼルエンジンがないため振動音がせず、静かで排ガスも臭わない。
岩谷産業の発足は1930年。創業者・岩谷直治氏が水素の販売を始めたのは41年で、LPガスの発売(1953年)よりも水素ビジネスの方が早い。日本の大型ロケットが燃料に使う液化水素は全て岩谷産業グループが供給している。水素燃料電池船「まほろば」建造は水素エネルギーのトップランナーとしての誇りをかけたプロジェクトだった。
比較優位保つ「燃料電池」

岩谷産業の会長兼CEOの牧野明次氏(左)と間島寛社長(同社HPより)
燃料電池は英ウェールズ出身で化学的素養を備えた弁護士のウィリアム・グローヴが1839年に開発した。水の電気分解の研究を続けていたグローヴは、幾つもの電極を組み合わせて様々な回路を試し、電気分解の逆反応で水素と酸素から電気と水を作り出すことができることを発見、「ガス・バッテリー」と名付けた。これが世界初の燃料電池である。
長らく日の目を見なかったが1960年代に宇宙開発レースの中でソ連と米国が宇宙船の電源として搭載し急速に技術開発が進んだ。化石燃料の燃焼を伴わないために二酸化炭素(CO2)が発生せず、水蒸気が出るだけ。閉鎖環境の宇宙船で使う電源として最適だった。
日本では70年代から国家プロジェクトとして「サンシャイン計画」(74~92年)や「ムーンライト計画」(78~92年)、「ニューサンシャイン計画」(93~2002年)の中で開発が進められた。
乾電池や蓄電池に比べて知名度は低かったが、2009年に東京ガスが世界で初めて家庭用燃料電池「エネファーム」を発売して以降、世間の知るところとなった。「エネファーム」は都市ガスから抽出した水素と大気中の酸素を反応させて発電する。その際に生じる熱で湯を沸かすことから「発電する湯沸かし器」と解釈することもできる。23年11月末に累計出荷台数が50万台を突破したが、資源エネルギー庁は30年迄に300万台の普及を目指しており、実情は遅れ気味だ。
14年にトヨタ自動車が燃料電池搭載車(FCV)の「ミライ」を発売して以降、政府はFCVにフォーカスした水素エネルギー普及策を打ち出した。日本の自動車は燃費性能の良さで海外メーカーを圧倒してきたが、電気自動車(EV)の台頭でエンジン車を軸とした優位性が揺らいでいる。燃料電池はエネルギー分野で日本が比較優位を保っている数少ない分野で、CO2を排出しないFCVならEVに対抗でき、自動車産業が競争力を維持できると判断したからだ。
「ミライ」の先進性は水素を詰める高圧水素ボンベにも表れている。3層構造で内側が樹脂、真ん中がCFRP(炭素繊維強化プラスチック)、外側がGFRP(ガラス繊維強化プラスチック)だ。高圧水素には金属に触れると内部に入り込んで強度を損なう「水素脆化(ぜいか)」という性質があるため、3種類の樹脂の合わせ技で封じ込めた。トヨタは「トヨタ高圧水素タンク」の名称で外販し、「まほろば」が採用した。昨年3月にクボタが発表した燃料電池トラクターもトヨタの高圧水素ボンベを3本積んでいる。
JR東日本は燃料電池とリチウムイオン電池を積んだ電車「HYBARI(ひばり)」を開発し、22年から南武線や鶴見線でテスト走行を続けている。トヨタが今年2月に発表した第3世代の燃料電池システムはディーゼルエンジンに並ぶ耐久性を備えており、トラックやバスなど商用車にも使える。欧州のエアバスは燃料電池搭載旅客機の開発に着手し、35年までに就航させる構えだ。
機械的駆動音を一掃

潜水艦「らいげい」(海上自衛隊公式チャンネルより)
陸海空の多様な輸送機器と組み合わせが可能な燃料電池だが、最も期待がかかるのは潜水艦だ。最新鋭のたいげい型は2022年に1番艦「たいげい」が就役した。建造費約800億円で全長84m、排水量約3000t。乗員は約70人で、女性乗員の専用区画も設けた。高性能・大容量のリチウムイオン電池を搭載し、ディーゼルエンジンで発電機を回し1度の充電で長時間航行できる。今年3月6日に海上自衛隊に引き渡された4番艦「らいげい」はディーゼルエンジンを新型に換装し、航行時間をさらに引き延ばした。建造費が702億円に下がり、建造工程の熟練度向上がうかがえる。
リチウムイオン電池の電気でモーターを駆動、スクリューを回す海自のディーゼルエレクトリック方式潜水艦は、常時原子炉の蒸気タービンを動かす原子力潜水艦に比べて静か。深海に潜み、ロシアや中国のミサイル原潜を監視し、迎え撃つのが任務だ。このディーゼルエンジンと発電機を燃料電池に置き換えれば機械的駆動音を一掃できる。
残るのはスクリューが水をかき回してできる泡がはじける際のキャビテーションという音だけだ。キャビテーションは潜水艦ごとに微妙に異なり、指紋ならぬ「音紋」をデータベース化して艦を識別する。スクリューがなくなれば「音紋」が生じないため潜水艦の識別が困難になる。
日本はキャビテーションを消す技術を持っている。1992年に三菱重工業と東芝が世界初の航行に成功した電磁推進船「ヤマト1」だ。住友電気工業製で直径20ミクロンのニオブチタンフィラメントを約1000本束ねて銅母材に埋め込んだものをコイルにし、超伝導磁石に仕上げた。
超伝導電磁石の磁界に対し垂直方向に電流を流すと「フレミングの左手の法則」の原理で水流が起きて推進力が発生する。ジェット推進はスクリューや変速機、シャフトなど機械的な動力機構がなくエネルギーロスが少ないため、海上を航行する船舶だと理論的には100ノット(時速約185㎞)の超高速船も可能だ。
米海軍の「シーウルフ級」原潜はポンプジェット推進で35ノット(同約64.8㎞)の高速を誇る。ただ電磁推進ではなくポンプジェット方式だから機械的騒音が出る。原子炉と蒸気タービンの音もする。
海上自衛隊が「まほろば」の水素燃料電池技術と「ヤマト1」の超伝導電磁推進技術を組み合わせた潜水艦を建造すれば、「リアル沈黙の艦隊」が誕生する。静かで高速航行が可能だ。しかも原子炉を積んでいないから反原子力勢力のクレームをかわせる利点もあり、いいことずくめなのである。