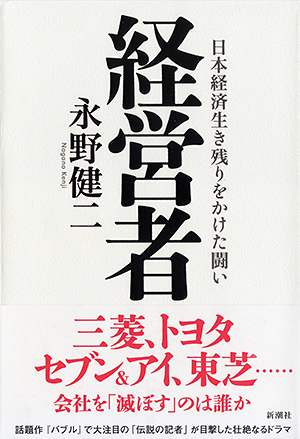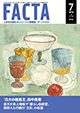『経営者 日本経済 生き残りをかけた闘い』
首肯せざるを得ない「経営論」異説
2018年7月号
連載
[BOOK Review]
by
秋場大輔
(ジャーナリスト)
四半世紀前、著者が私の上司になった。まだ駆け出しに毛が生えたくらいだったので、周囲にどんな人なのかを尋ねると、いくつか伝説を教えてくれた。「野村の田淵(節也元社長)の家に宿泊用の寝巻が置いてある人」「大蔵省の内情に精通しているので、どうやって情報を入手しているのか、彼を尾行した後輩がいる」
その伝説の記者の下で仕事をするようになったある日、神保町の外れにある喫茶店に連れて行かれた。フリージャーナリストと落ち合い、「オオタブとメシを食ったら、こんなことを言っていた」「ナガオカさんと飲んだ時にさあ……」などと話し込んでいた。割って入るほどの情報を持っているはずもなく、黙って聞いているしかなかった。
本書は日本の経済社会を動かした、もしくは動かしている経済人に直接会って議論を交わし、本音を聞き出した著者が17人の経営者を評価した1冊である。
経営者が何者なのかを描いた本はあまたある。しかしほとんどは同じ史実、エピソードに浅薄な洞察を加えたものだから、紡ぎ出される人物像は同じ。対して本書は著者しか知らないエピソードがふんだんに盛り込まれ、そこに二ひねりほどされた洞察が加えられているため、一見、異説に見えるが首肯せざるを得ない説得力を持つ。
著者は、経営者という枠を超え、公益のために生きた小倉昌男が終戦からヤマト運輸に入社するまで、人工甘味料「サッカリン」を製造・販売するヤミ屋を営み、儲けていたことを記す。その上で「本人が照れながら語らない、あるいは首尾一貫していないと思われる行動にこそ、『精神』が浮き彫りになる」と指摘し、小倉のプラグマティックな手腕こそ語り継ぐべきことではないかと書く。
小倉率いるヤマトは1979年に三越の配送業務から撤退し、宅配事業に社運をかけた。著者は、その決断はヤマトにとって本当の顧客がBtoBからBtoC、さらにCtoCへと移り変わる流通社会の変化を見据えたものだったと分析している。
企業の大きな決断が何を意味するのか。その分析がミクロジャーナリズムの生命線だが、得てしてステレオタイプな意義付けに終わる。取材不足だからであり、目の前の事実をどう捉えるべきか、頭から血が出るほど考え抜いていないからだ。
冒頭に書いた神保町の喫茶店の話には続きがある。オフィスに戻る途中、著者がふいに「お前の年収はいくらだ」と聞いてきた。正直に答えると、「さっきまで一緒だったジャーナリストはお前より少ない稼ぎであれだけ詳しい。恥を知れ」と言われた。あの一言が記者人生の原点になっている。
BOOK Review バックナンバー
- 命を削る労作「調査報道150選」 (2026年03月号 )
- 私と母の秘密の思い出「砂川闘争」 (2026年02月号 )
- 真相解明のためなら何でもやる矜持! (2026年02月号 )
- 苦悩する「豊田章男」と紡ぐ言葉 (2025年12月号 )
- 政権中枢の「証言の数々」に刮目 (2025年08月号 )
- 申し訳ないが「読者を選びます!」 (2025年08月号 )
- 『なぜ倒産 運命の分かれ道』 (2025年03月号 )
- 超カリスマ池田大作の「黒い履歴書」 (2025年02月号 )
- 地方を元気に!「奇跡の酒蔵移転」の実録 (2024年12月号 )
- 「オバマ広島訪問へ」突き付けた切り札 (2024年12月号 )