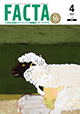「廃炉」という幻想―福島第一原発、本当の物語
原発推進にも反原発にも与しない力作 著者:吉野実/評者:田中俊一 初代原子力規制委員会委員長
2022年4月号
連載
[BOOK Review]
by
田中俊一
事故から11年経っても、福島県民には復興への実感もなく、展望もない。その原因の一つが福島第一原発の廃止措置が迷走し、全く先行きが見えないことである。無残に壊れた原発は、住民の不安要因の一つで、当初の混乱した状況から改善されたといっても、住民にとっては敷地内で何が行われ、何が起こっているかが全く分からないお化け屋敷というのが実感である。
福島第一原発事故に関する著作やメディア報道の多くは、現地の実態の裏付けもなく、先入観に基づく他人事の評論に終わっており、「福島の現実は違うよ」と苛立ちを感じることが多い。
福島の復興との名を借りて原発の賛否のために福島を利用するものも少なくない。
本書は「原発推進側にも、反対の立場にも与しない」と述べ、あくまでも福島第一原発の廃炉の課題を技術的、政策的な観点から明らかにすることに主眼をおいている点で、他の著書とは全く異質である。とりわけ、職業柄とはいえ事故から11年、幅広い視点からの取材を通して感じたことを、丹念に裏付けをとるだけでなく、自らの科学的判断について慎重に確認していることが読み取れる。
国と東電が「30年から40年で廃炉ができる」と主張しているが、デブリの取り出しは、技術的な裏付けのない約束であり、再考すべきことを事実に基づいて指摘している。さらに、廃炉の課題の中では、もっとも容易であるべきトリチウム処理水について、排水からのトリチウム水を分離し、あたかも適切な処理方法があるかのごとき無責任な議論を6年間も繰り返し、この間に凍土壁や無数のタンクを設置しただけで、未だに明確な展望が抱けない状況についても著者のやりきれない苛立ちが表れている。
「廃炉という幻想」は、著者の10年にわたる取材とそれを裏付ける専門的な学習の中から湧き出た国や東電、そこに取り巻く専門家への怒りと憤りだけでなく、福島県、県民、あるいは国民に対する著者の思いの凝縮であると想像できる。その上で、1Fの廃炉の先行きは、明確に展望できないことを踏まえ、「廃炉の本当の未来」を拓くためには、すべての事実を開示し、廃炉が長期化することを素直に認め、誠実に説明し、住民の理解と協力を得ることが必要であるとしている。最近、新たな原発の必要性を主張する声がでてきているが、1F事故についての厳しい反省と県民が納得できる廃炉が大前提である。
著者の住民に対する熱い思いと優しさが凝縮されている力作で、国や東電の関係者には一読することを強くお勧めする。
BOOK Review バックナンバー
- 命を削る労作「調査報道150選」 (2026年03月号 )
- 私と母の秘密の思い出「砂川闘争」 (2026年02月号 )
- 真相解明のためなら何でもやる矜持! (2026年02月号 )
- 苦悩する「豊田章男」と紡ぐ言葉 (2025年12月号 )
- 政権中枢の「証言の数々」に刮目 (2025年08月号 )
- 申し訳ないが「読者を選びます!」 (2025年08月号 )
- 『なぜ倒産 運命の分かれ道』 (2025年03月号 )
- 超カリスマ池田大作の「黒い履歴書」 (2025年02月号 )
- 地方を元気に!「奇跡の酒蔵移転」の実録 (2024年12月号 )
- 「オバマ広島訪問へ」突き付けた切り札 (2024年12月号 )