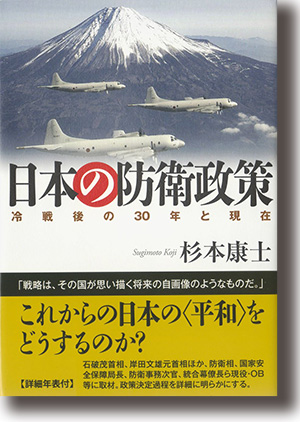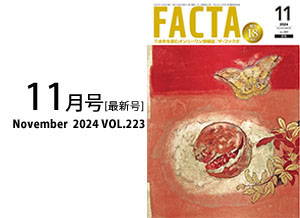政権中枢の「証言の数々」に刮目
『日本の防衛政策』 冷戦後の30年と現在 著者/杉本康士 評者/園田耕司
2025年8月号 連載 [BOOK Review]
産経と朝日という対極的な主張の新聞社にいながらも、杉本康士氏は私の深く敬愛する畏友である。
そのきっかけはちょうど10年前、ともに米ハーバード大学日米関係プログラムの客員研究員を務めたことにある。ブログラムが始まる直前の夏の間、杉本氏と私はボストン大学の古びた学生寮に入って語学研修を受けることになったが、たまたま2人一部屋のルームメートとなった。中東地域の士官学校から来た若者たちが寮内で繰り広げる夜な夜なのどんちゃん騒ぎに悩まされながらも、言葉通り、寝食を共にして勉学に励んだ。
それ以来、ともに外交安保問題を専門としていることもあり意気投合し、親しく付き合うようになった。時に熱い議論を交わしながら、私はいつも杉本氏の持つ専門的な知見に驚かされていた。理想的な国家像への熱い思いを胸に抱きつつも、リアリスト的思考を兼ね備えた彼の問題意識は、私にとって大いに刺激になるものだった。
その杉本氏の安全保障問題に対する卓見が存分にあらわれているのが、本書である。日本政府は「ポスト冷戦期」の1995年以降、計6回にわたり防衛大綱などの戦略文書を改定していたが、それがどのような過程をたどって形成されてきたのかを徹底的に検証。なぜ日本が中国の脅威を真正面から見据え、南西諸島防衛強化の方針を打ち出し、打撃力の保有や防衛費の大幅増額を決断するに至ったのかを解き明かすものだ。
圧巻は、何と言っても、岸田文雄前首相を筆頭に、石破茂氏ら歴代防衛相、政府高官、自衛隊制服組と実際に日本の防衛政策を形作ってきた人々の貴重な証言をもとに、30年間にわたる防衛政策の変遷を生き生きと描き出している点にある。
安保政策を巡る歴史を政権中枢にいた関係者の証言でつづったものに、読売戦後史班による名著『昭和戦後史-「再軍備」の軌跡』(中公文庫)があるが、本書はこれに匹敵するものと言っても良い。日々の深い取材をもとに日本の安全保障コミュニティーにおいて幅広いネットワークをもつ杉本氏だからこそ書けた内容だろう。
本書のもう一つの特徴がアカデミックな検証に堪えられるように、取材日時を含めて徹底した注釈を入れていることにある。日本の政治ジャーナリストが著す本には、注釈に十分な配慮がなされていないことが多い。この点がボブ・ウッドワード氏らアメリカの著名な政治ジャーナリストの著す本と比べて見劣りすると残念な指摘を受けることがある。本書はアメリカジャーナリズムと同様に徹底した注釈を入れて検証可能にしている点で、日本の政治ジャーナリズムの新たなモデルを作っていこうという著者の強い意欲を感じる作品だ。
杉本氏はこう記す。「おそらく、10年後、20年後、30年後には、より多くの資料が公にされ、より多くの証言も集まり、より精緻な検証が歴史家の手によってなされるであろう。しかし、戦略は、出来上がったその日から書き換えの作業が始まる。〈中略〉利用可能な証言と資料を使い、できる限り早く、できる限りの範囲で政策決定過程を明らかにすることが新聞記者である私の仕事だと考えた」。政権中枢の生々しい証言に基づく優れたドキュメントでもある本書が、後世にわたって貴重な歴史的記録として読み継がれていくのは間違いない。
■評者プロフィール
BOOK Review バックナンバー
- 申し訳ないが「読者を選びます!」 (2025年08月号 )
- 政権中枢の「証言の数々」に刮目 (2025年08月号 )
- 『なぜ倒産 運命の分かれ道』 (2025年03月号 )
- 超カリスマ池田大作の「黒い履歴書」 (2025年02月号 )
- 地方を元気に!「奇跡の酒蔵移転」の実録 (2024年12月号 )
- 「オバマ広島訪問へ」突き付けた切り札 (2024年12月号 )
- 「安倍発言」にメルケルが木槌を打った瞬間 (2024年11月号 )
- 上質のミステリーのような切れ味 (2024年07月号 )
- 中国の先端宇宙開発を読み解く (2024年07月号 )
- 「米中衝突」回避するための処方箋 (2024年05月号 )