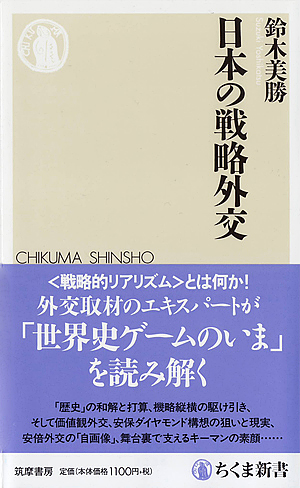『日本の戦略外交』
「正念場の安倍外交」に渾身の訴え
2017年4月号
連載
[BOOK Review]
by
村田晃嗣
(同志社大学教授)
本書は、吉田茂と岸信介の系譜から説き起こしながら、冷戦後の日本外交を「戦略的リアリズム」や「戦略外交」という観点から分析する試みである。とりわけ、「戦略的猶予期間」としての1990年代と比較しつつ、安倍晋三政権の外交を縦横に論じている。
「戦略」や「戦略的」の定義は、論者によって実に多様である。おそらく、戦略概念の比較論だけで、いくつもの博士論文が書けるであろう。本書では、著者は骨太に戦略的空間と戦略的時間軸を描き出し、両者を結びつけて活用できる指導者の胆力について語ろうとしている。
先述のように、1990年代は、冷戦後の国際環境に対応し、新たな秩序を構築し、戦略を編み出す「猶予期間」のはずであった。しかし、国内的な混乱もあって、日本はこれを活用できないまま、2001年9月11日の同時多発テロ以降の激動に突入していった。
やがて、第一次安倍政権では、麻生太郎外相が「自由と繁栄の弧」の名の下に価値観を重視する外交を展開しようとした。この発想は、第二次安倍政権でも、「地球儀俯瞰外交」として継承されていく。こうした新たな外交上の取り組みの背後には、プロの「黒子」たちがいた。谷内正太郎をはじめ、兼原信克、谷口智彦らである。谷内と兼原は戦略志向の外交官であり、谷口はジャーナリストから転じた表現力豊かなスピーチライターである。ベテランのジャーナリストとして、著者はこうした「黒子」たちの貢献を活写している。
本書のもう一つの特徴を挙げれば、著者が外交専門誌の編集長を長らく務めたことから、若手研究者らの優れた分析や概念を積極的に取り入れ紹介していることである。ジャーナリズムの現場力とアカデミズムの分析力が、本書の中でうまく融合している。
さて、第二次安倍政権は、戦略的空間を点と線から面と立体に拡大し、中国を念頭に日米豪印の「安保ダイヤモンド構想」を提唱するなど、野心的であった。だが、そこに歴史認識問題という情念のドラマが、戦略的時間軸で日本外交を揺さぶった。第一次政権の挫折から胆力を養った安倍は、自我を抑えながら日米関係や日韓関係、そして、日ロ関係の改善に布石を打っていく。こうして、戦後70年談話や従軍慰安婦問題をめぐる日韓合意、そして、バラク・オバマ米大統領によるヒロシマ訪問が達成されていった。だが、アメリカは大統領選挙でドナルド.トランプという劇薬を選択した。日米の価値共有のみならず、日本の戦略外交全体が再考を求められるようになった。そうした中で、中国は2021年の中国共産党100周年と49年の中華人民共和国建国100周年を目標に、アメリカと肩を並べる大国化の道を歩もうとしている。それに対して、2020年の東京オリンピック以降に、安倍外交は戦略的時間軸の中に有意な目標設定をしうるであろうか。日本外交は今まさに正念場にある――本書は達意のジャーナリストの渾身の訴えである。
BOOK Review バックナンバー
- 苦悩する「豊田章男」と紡ぐ言葉 (2025年12月号 )
- 政権中枢の「証言の数々」に刮目 (2025年08月号 )
- 申し訳ないが「読者を選びます!」 (2025年08月号 )
- 『なぜ倒産 運命の分かれ道』 (2025年03月号 )
- 超カリスマ池田大作の「黒い履歴書」 (2025年02月号 )
- 地方を元気に!「奇跡の酒蔵移転」の実録 (2024年12月号 )
- 「オバマ広島訪問へ」突き付けた切り札 (2024年12月号 )
- 「安倍発言」にメルケルが木槌を打った瞬間 (2024年11月号 )
- 上質のミステリーのような切れ味 (2024年07月号 )
- 中国の先端宇宙開発を読み解く (2024年07月号 )