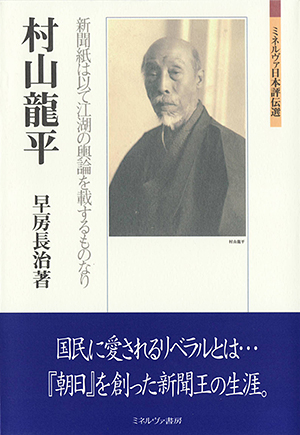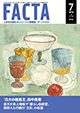『ミネルヴァ日本評伝選 村山龍平 新聞紙は以て江湖の輿論を載するものなり』
左から右まで「リベラル新聞」の祖
2018年7月号
連載
[BOOK Review]
by
大鹿靖明
(朝日新聞記者)
朝日新聞社の創業者である村山龍平の評伝を同社OBの著者がコンパクトにまとめた。村山は、田丸藩士の家に生まれた武士階級の出だが、明治維新後、さっさと商人に転身。「武家の商法」で零落する者が多かったのに、いち早く大阪に出て、舶来品の輸入販売で成功する。次いでランプ用の石油輸入会社も創業。商機を見いだして手を広げるのは、今日の孫正義、三木谷浩史らベンチャー経営者に通じるものがある。
関西財界で名をなした村山に、経営難の朝日新聞を引き受けてくれと依頼があったのが、同紙創刊2年後の1881(明治14)年。つまり記者でも編集者でもない彼は、「経営の才」を見込まれて新聞人となった。ジャーナリストの素地がなかったにもかかわらず、引き受けるやいなや売れる新聞づくりを意識したのが面白い。ライバル社からスター記者を引き抜き、重要地に特派員を派遣。電報多用によって東京の最新情報を速報。そして翌年、「吾朝日新聞の目的」として「江湖の輿論を載するものなり」と、その目指すべき方向性を位置づけた。
著者の早房長治は、村山のめざしたものを「リベラルな新聞」と評する。いま「リベラル」という用語は、「左派」「左翼」の代用の響きがあるが、早房の使うリベラルとはそうではなく、「多様な言論を保証する寛容さ」。つまり左から右までの「言論の幅」のこと。「民主主義の要諦は煎じ詰めれば言論の幅」と早房は言う。特定の主義主張を振りかざす当時の政論新聞とは異なり、村山は「江湖の輿論」として国粋主義の三宅雪嶺、杉浦重剛から大正デモクラシーの旗手の吉野作造や大山郁夫まで幅広い人材を起用した。人材発掘能力に秀でた人だったのだ。安倍政権下、言論が真っ二つに割れる今日こそ、そんな懐の深いメディアが求められよう。
村山にも負の側面がある。ひとつは、研究者の間では知られたことだが、朝日は創刊間もないころ明治政府から秘密裏に財政支援を受けていたこと。反政府運動に偏らないようカネで手綱を引かれていたのだ。
そして肝心なときにトップの村山が弱腰なことだ。言いがかりに過ぎない白虹事件で右翼と官憲に屈服。後年には、招聘した吉野作造の講演を右翼に難癖をつけられると、これも完敗。記者たちの楽園と思えるほど自由闊達な社風の半面、経営トップの意気地のなさは以来、朝日の伝統か。外部からの批判を過剰に恐れ、紙面や記者を守らない小心翼々の社長。過去の報道を修正し、ときの首相の歓心を買おうとした社長……。映画『ペンタゴン・ペーパーズ』で描かれたワシントン・ポストの女性社主の気概とは大違いである。
BOOK Review バックナンバー
- 私と母の秘密の思い出「砂川闘争」 (2026年02月号 )
- 真相解明のためなら何でもやる矜持! (2026年02月号 )
- 苦悩する「豊田章男」と紡ぐ言葉 (2025年12月号 )
- 政権中枢の「証言の数々」に刮目 (2025年08月号 )
- 申し訳ないが「読者を選びます!」 (2025年08月号 )
- 『なぜ倒産 運命の分かれ道』 (2025年03月号 )
- 超カリスマ池田大作の「黒い履歴書」 (2025年02月号 )
- 地方を元気に!「奇跡の酒蔵移転」の実録 (2024年12月号 )
- 「オバマ広島訪問へ」突き付けた切り札 (2024年12月号 )
- 「安倍発言」にメルケルが木槌を打った瞬間 (2024年11月号 )